このブログでは、季節に合わせた薬膳食材をご紹介しています。
2025年3月20日(春分)〜5月5日(立夏)の期間を『春の薬膳』としています。
人参とは
なぜ『人参』と呼ばれるようになったか
中国で「人参」というと、朝鮮人参(高麗人参)を指します。「人の形をした根」という意味から由来しているようですね。
一方、私達が食用と認識しているオレンジ色の人参は、「コラフク(胡蘿蔔)」と呼ばれています。「胡」は中国で「外国」、「蘿蔔」は根菜を指しますので、「胡蘿蔔」は「外国から来た根菜」という意味です。実は日本でも、江戸時代頃までは人参を「コラフク」と呼んでいました。
朝鮮人参は、日本には飛鳥時代に中国から薬用植物として伝わり、滋養強壮などの医薬目的で利用されていました。
室町時代になると、中国から「東洋種」の長い人参が「コラフク」として渡来し、日本各地で栽培されるようになりました。
「コラフク」は江戸時代初期には庶民の台所でも使われるほど広く普及しました。
この頃、「コラフク」は葉が芹(セリ)に、根が朝鮮人参に似ていることから「芹人参」と呼ばれるようになりました。これには「日本独自の名称で呼びたい!」という文化的背景もあったようです。
さらに江戸時代後期になると「芹」も簡略化され、結局「人参」という名称に落ち着きました。朝鮮人参と区別するためわざわざ「芹人参」と呼んでいたのに…。
そして明治時代に「西洋種」の人参(オレンジ色の人参)が導入され、形状が短く扱いやすいことから東洋種に取って代わりましたが、「人参」という名称はそのままで現在に至ります。
人参の歴史
オレンジ色の人参の原産地は、中央アジアのアフガニスタン周辺。古代には紫色、黄色、白色など多様な色が存在していました。
オレンジ色の人参が誕生したのは16世紀末、オランダでのこと。甘みが強く害虫に強い品種を目指して改良を重ねた結果、オレンジ色の人参が生まれたそうですが、実はオランダ王室「オラニエ=ナッサウ家」に敬意を表して作られたとも言われています。当時のオランダの3色旗は、オレンジ・白・青だったようです。
19〜20世紀にかけて、オレンジ色の人参に豊富な栄養素(特にβカロテン)が含まれることが科学的に証明され、世界中で広く栽培されるようになりました。現在ではオレンジ色の人参が主流となり、その栄養価と甘みから世界中で愛されています。
人参は「苦手な野菜」
その一方、人参は「苦手な野菜」トップ10の常連でもあります。苦手に感じるポイントは、やはり「甘みと青臭さのバランス」でしょう。
人参は甘みが強い野菜ですが、一方で青臭さもあります。この微妙なバランスが、人によっては苦手に感じる要因になっているそうです。人参にはβカロテンが豊富に含まれており、これが独特の風味を生む原因のひとつです。とくに生や加熱が不十分な場合に「土臭さ」や「青臭さ」を感じやすいそうです。
畑の直売所や道の駅、少しお高めの八百屋やスーパーで販売されている人参は独特の風味を強く感じるけれど、近所のスーパーで購入できるようなお手頃価格の人参は味が薄く、多少の甘味はあるけれど青臭さはあまり感じません。人参ジュースにすると、その違いがよく分かります。特に有機栽培されたものは独特の風味が強く、いかにも「栄養たっぷりです!」という味がします。
鮮度や品種、季節による違いもありますが、大量生産される人参は青臭さを控え、均一な甘さを重視する傾向があると言われます。好みにもよるけれど、私はジュースには人参臭さがないとつまらないと感じてしまいます。
人参の栄養価
学校給食では、ほぼ毎日のメニューに人参が使用されているそうです。煮物、スープ、サラダなど多様な調理法で使いやすいという理由もありますが、栄養バランスが良いというのがいちばんの理由でしょう。突出して含有量の多いβカロテン以外はそこそこの栄養価なのですが、例えば食物繊維にしても水溶性が不溶性1:2〜3と(理想は1:3)子どもの成長に必要なビタミンやミネラルをバランスよく含んでいます。
大人が人参を食べるのなら、やはりβカロテンを効率よく摂取したいですね。人参には、皮側にβカロテンが多く含まれています。人参は芯を通じて養分が中心部→葉へと送られるため、時間が経つと中心部は栄養素が抜け、ほぼ食物繊維のみになってしまいます。
そのため、人参を選ぶ時は、ヘタがなるべく小さいもの(=葉に送られる栄養の通り道が狭い。成長するにつれて太く、ヘタが大きくなっていく)を選ぶと栄養価が高いです。
人参の皮は非常に薄く、出荷前の洗浄時にほとんどの皮が取り除かれるそうですが、完全に取り除かれるわけではないので、残留農薬が気になるならば皮は剥いた方が良いと思います。私は「日本の厳しい残留農薬の基準値をクリアしているなら大丈夫!」という考えで、あまり気にしていません。ちなみに多くの人が人参の「皮」と認識している部分は、実は皮ではなく「内鞘細胞」という可食部の一部です。
人参の栄養をいちばん効率よく摂取できるのは、「皮付きのまま・加熱して・油と一緒に」食べるような調理方法です。生の人参に含まれる酵素「アスコルビナーゼ」にはビタミンCを酸化させてしまう働きがあり、他の食材が持つビタミンCの吸収を悪くしてしまいます。また、人参の代表的な栄養素であるβカロテンは、生の状態で食べても身体に吸収されにくく、①加熱すること②油と一緒に摂ることで吸収率が一気に上がります。
よしながふみさん著『きのう何食べた』11巻に登場するレシピで、元は栗原はるみさんのレシピをアレンジしています。私は両方のレシピで作るうち、中間くらいに定着しました。
① 人参1本は千切り、玉ねぎ1/4個はみじん切りにして耐熱ボウルに入れ、鶏ガラスープの素小さじ1・サラダ油またはオリーブ油大さじ1を加え、軽く混ぜる。
② ふんわりラップをして600wのレンジで2分加熱する。
③ 酢大さじ1・レモン汁大さじ1・粒マスタード大さじ1・だし醤油小さじ1を加え、混ぜる。
④ 汁気を切ったツナ缶とパセリ大量を加えて混ぜ、黒胡椒をかける。
人参の薬膳効能

『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』元気幸房代表 竹内郁子編著:ブイツーソリューション出版より
人参は目の疲れ、乾燥、かすみ、視力低下などを改善する効果があると言われています。
人参は『肝』の『蔵血』を助け、肝血虚による目の症状を改善する効果があると考えられています。
「春の薬膳」で解説したように、中医学では、自然界や人体を『五行(木・火・土・金・水)』に当てはめて分類します。これを人体のいろいろな部分に当てはめると以下のようになります。
| 五行 | 五臓 | 五主 | 五官 | 五華 |
| 木 | 肝 | 筋 | 目 | 爪 |
| 火 | 心 | 脈 | 舌 | 面 |
| 土 | 脾 | 肌肉 | 口 | 唇 |
| 金 | 肺 | 被毛 | 鼻 | 毛 |
| 水 | 腎 | 骨 | 耳 | 髪 |
上の表から分かるように、春に起こりやすい「肝の不調」による血虚や陰虚は、「筋、目、爪」に症状が現れやすくなります。
・筋の症状…足がつる
・目の症状…疲れ、乾燥、かすみ、視力低下
・爪の症状…爪が白い、割れやすい
人参はとくに目を潤す力が強く、長時間のパソコン作業やコンタクトレンズ使用によるドライアイ、充血などにも効果的です。
栄養価でいうと、βカロテンを豊富に含みます。βカロテンは抗酸化作用や免疫力を上げる作用のほか、体内でビタミンAに変換され、粘膜を丈夫にしたり、髪・爪・皮膚の細胞を活性化させる働きがあります。
また網膜で光を感じる物質「ロドプシン」を作る働きもあるため、不足すると夜盲症(暗い場所で目が見えにくくなる症状。通称「鳥目」)を引き起こす可能性があります。
βカロテン由来でない動物性由来のビタミンAの過剰摂取は毒性を持つ可能性がありますが、植物性由来のβカロテンは体内で必要量だけビタミンAに変換されるため、毒性リスクが少なく安心してたくさん食べることができます。
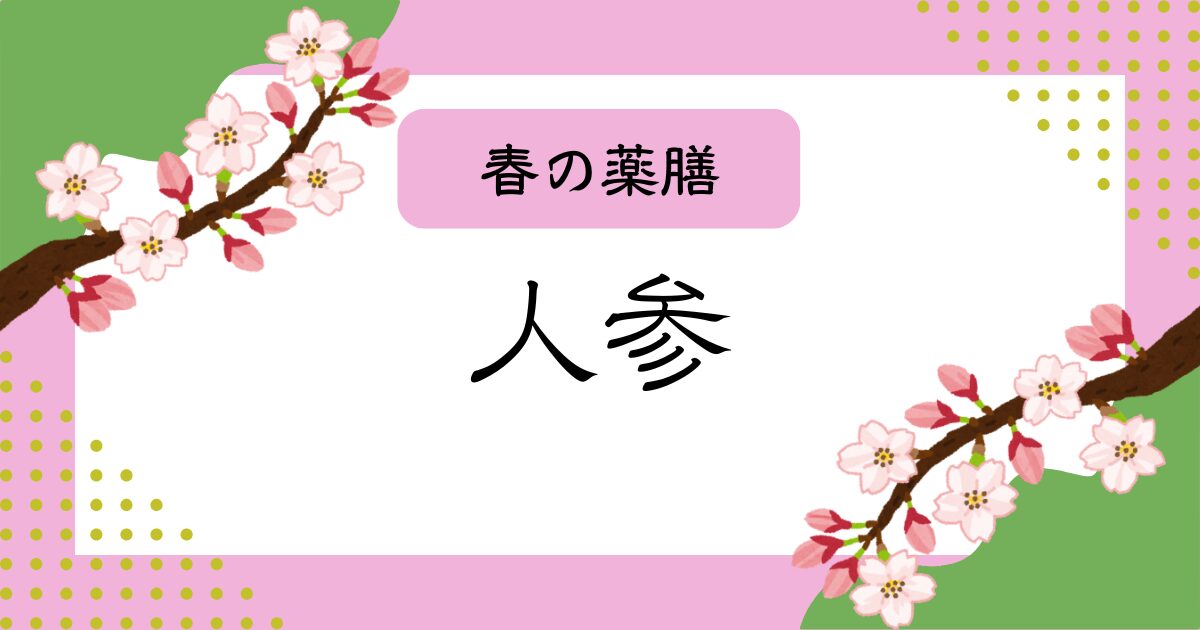
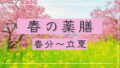
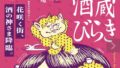
コメント