このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。
2025年2月3日(立春)〜3月20日(春分)の期間を『早春の薬膳』としてご案内しています。
ニラについて
ニラの旬
阿川佐和子さんのエッセイ『残るは食欲』シリーズの『魔女のスープ』のなかに、「ニラは2月」という印象的なエピソードが登場します。阿川佐和子さんの父・阿川弘之さんが学生のころ、中国語教師に「北京では2月のニラがいちばん美味しい」と教わり、それが子どもたちにも引き継がれ、毎年2月になると「少しでも多くニラを食べなければ」という焦燥感にかられる…という内容でした。これを読んで以来、私のなかにも「ニラは2月」がインプットされました。実際、早春の頃のニラの一番取りは、やわらかくて香り高く、本当においしいと思います。
ニラは多年草で成長が早く、1〜3ヶ月ごとに収穫が可能です。暖かい時期(春〜秋)であれば年に3〜5回は収穫できるため、どの時期のニラを旬とするかは食感などの好みによります。
ニラの家庭菜園
ニラは暑さ・寒さに強く、家庭菜園できるくらい栽培が簡単です。苗を植えて2〜3ヶ月もすれば収穫でき、根元を残して刈り取ればまた新しい葉がのびてきます。冬場は一見枯れたようになりますが、春になるとまた新しい葉が出てくるため、同じ株で4〜5年は持ちます。なにしろ、本格的に栽培されるようになったのは昭和40年頃で、それまでは各家庭の庭や田んぼのあぜ道で収穫されていたという手軽さです。我が家でもプランターでニラとネギを育てています。
栽培については、たくさんの方がYouTubeで紹介されていますが、私は『ズボラ菜園家ぽたろう』さんの解説がいちばん分かりやすかったです。
『ぽたろうの家庭菜園HACK』
【コスパ無限大】ニラ栽培690日で判明したベランダでニラが大活躍する理由/ニラの育て方
https://youtu.be/jMSwIFxQ-Qk?si=pD77drhgDUZmHDlJ
本日のレシピ:ニラ豚(私流にアレンジしたもの)
ニラは生のまま冷凍可能なので、洗ってペーパータオルでしっかり水気を拭き取り、調理に使用する長さに切ってから蓋付きの保存容器に入れて冷凍します。完全に凍ってから、蓋をしたままで保存容器を振ると、きれいにバラけて使いやすくなります。
『魔女のスープ』には『ニラ豚』という料理が登場します。ニラと豚肉を炒めて醤油で味付けするだけというシンプルなレシピで、とてもおいしいのですが、今の時期よりも夏にピッタリな一品です。初夏〜夏にかけて収穫される二番取り、三番取りされたニラは少しかための食感ですので、炒めるとシャキシャキとして歯応えが良いですし、豚肉と合わせることで疲労回復効果抜群のスタミナメニューとなります。私はレバーが苦手なので、レバニラの代わりに夏の間しょっちゅう作ります。

① フライパンにごま油を強火で熱し、豚肉100g(バラでもコマでもひき肉でも)を投入します。
② ニンニクと生姜(みじん切り)、醤油大さじ1、味の素3振りで味付けします。
③ 玉ねぎ1/2個分(薄切り)と、ニラ1束分の根本部分(ざく切り)を投入します。
④ 玉ねぎが色付いたら残りのニラを投入します。
⑤ 仕上げにオイスターソース大さじ1。最後までずっと強火です。
本日のレシピ:ニラ玉
やわらかい春のニラは、サッと茹がいて食べるような料理がおいしいと思います。お浸しや和え物、生の葉をザクザク刻んで味噌汁の実にするなど。私がよく作るのはニラ玉です。炒めて作るレシピも多いのですが、私にとってニラ玉とは「ニラを出汁で煮て玉子でとじたもの」。やはり実家の味がそのまま受け継がれるものですね。東海林さだおさんも『ゴハンの丸かじり』で同じような内容のエピソードを書かれており、ファンとしてうれしく拝読しました。このブログを書くにあたって久しぶりに読み返しましたが、「里芋のヤマちゃん」のくだりでお茶を吹きそうになりました。

① 鍋に「飲んでおいしい」くらいに味付けしただし汁を沸かします。
※だし汁の分量は「春菊」をご参照ください。
② ニラを入れ、すぐに溶き卵をまわしかけ、弱火で30秒加熱します。
③ 蓋をして火を止め、1分蒸らします。
ニラの薬膳効能
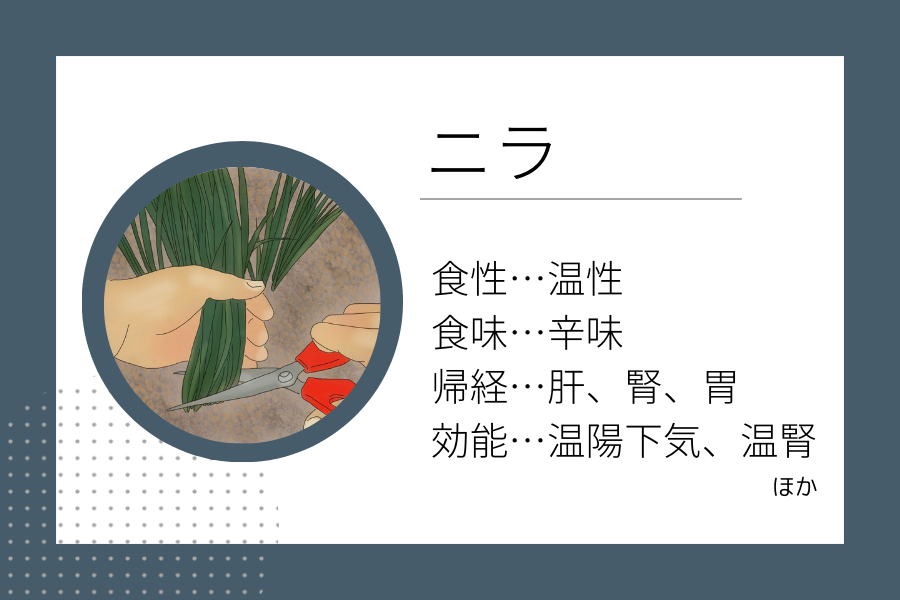
ニラは身体を温め、血をきれいにして、身体中にめぐらせる効果があると言われています。
『五臓』のひとつである『腎』は、生命力の源とされており、成長・発育・老化に深く関わっています。腎の機能が衰えると、子どもであれば発育不良、大人であれば老化の加速につながります。そのため、若々しく健康に生きるためには腎の機能を正常に保つことが大切だと考えられています。
『五臓』にはそれぞれ陰と陽のエネルギーがあり、『腎』の陰陽はどちらも不足しやすいという特徴があります。そのため、腎の機能を正常に保つためには、『腎陰』『腎陽』を補うことが重要となります。とくに『腎陽』は身体の熱源のような役割を持つため、腎陽が不足すると冷え性になりやすくなります。
ニラには、腎陽を補い、身体を内側から温める作用があります。そのため「起陽草(きようそう)」とも呼ばれ、冷え性の改善や足腰の冷えに効果を発揮します。ちなみにニラの種「韮子(きゅうし)」は、中医学で「助陽薬」として扱われ、さらに強力な温め作用が期待されます。
また、ニラには血を浄化し全身にめぐらせる効果があります。
ニラは、葉先にはビタミンAやCを、根本にはアリシンを豊富に含みます。アリシンはニンニクや玉ねぎにも含まれている成分で、ビタミンもアリシンも血液をサラサラにして血流を良くする作用があります。
中医学では、血の巡りが悪くなると筋肉が硬くなり、肩こりが起こると考えられています。ニラには血のめぐりを良くする作用に加え、「舒筋(じょきん)」という、筋肉をしなやかにする作用もあり、肩こりの改善にも効果的です。
おすすめの薬膳書籍
薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。
複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。
|
先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版 新品価格 |
 |
![]()
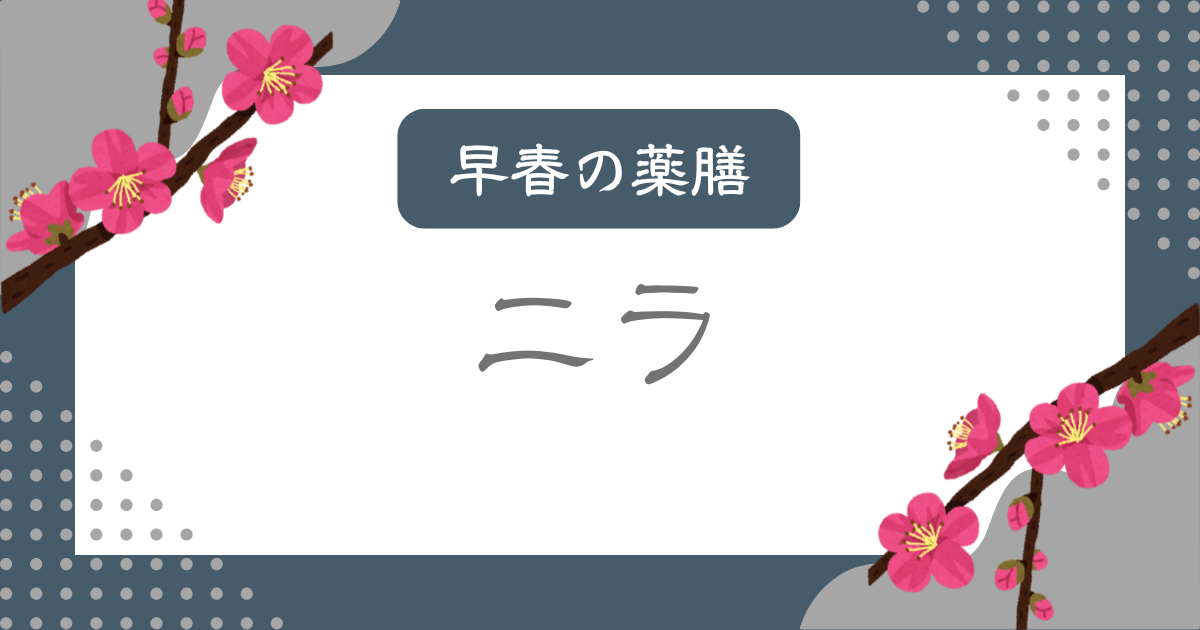


コメント