今日は立夏。端午の節句でもありますね。
5月は田植えが始まる月です。「皐月」の「皐」という字には、「田の神様に奉納する稲」という解釈があります。昔は5月はじめの午の日である「端午の日」に、魔を祓う香気を持つ菖蒲やヨモギを軒先に吊るして、湯や水に入れて禊を行い、田の神様を迎えたといわれています。
鎌倉時代になると、菖蒲を「尚武(武事・軍事を重んじること)」にちなんで、武家で盛んに祝われるようになりました。男児の成長と出世を祈る意味を込めて兜や鎧を飾る風習が生まれ、次第に「男の子のための行事」となったそうです。その後、江戸時代に「五節句」が制定され、「女の子は3月3日、男の子は5月5日にお祝いをする」という習慣が公式化されました。
このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。
2025年5月5日(立夏)〜6月11日(入梅)の期間を『初夏の薬膳』としてお届けします。
初夏に起こりやすい不調
朝晩の寒暖差はまだありますが、日中はかなり暖かくなってきましたね。ゴールデンウィークが終わる頃には、福岡の気温も安定します。連休中は衣替えやエアコンの掃除、虫対策など、夏支度で大忙しでした。
連休明け頃から「なんとなく気持ちが落ち込む」「やる気が出ない」「だるい(疲労感)」「集中できない」といった不調を感じる人が増えてきます。いわゆる「五月病」と呼ばれるもので、西洋医学では適応障害や軽度うつ状態、時には情緒不安定や自律神経失調症と診断されることもあります。
中医学では、新生活に伴うストレスで『肝』がダメージを受け、その働きの一つである『疏泄(めぐらせる)』機能が低下し、気のめぐりが悪くなって『気滞(肝気鬱結)』になると考えられます。
『肝気鬱結』と『肝陽上亢』
・ イライラ、情緒不安定
・ 消化不良、胸焼け、胃もたれ(食べ物のめぐりが悪くなる)
・ 喉や胸のつかえ感、梅核気(喉に何か引っ掛かったような感じ)
・ 胸脇部(肋骨の下の辺り)の張ったような痛み
『気滞』は熱を持つため、『肝気鬱結』が進行すると、やがてドカンと爆発します。これを『肝火』と呼び、ヒステリーを起こしたり、熱が上昇して頭部にも影響を及ぼします。これを『肝陽上亢(かんようじょうこう)』と呼びます。
・ ヒステリーや怒りっぽさ
・ 偏頭痛、めまい
・ 顔のほてり、目の充血
初夏の薬膳のおすすめ食材
『肝気』の高ぶりを鎮め、『疏泄』機能を回復させる食材です。
- 香りの良い野菜やハーブ(セロリ、せり、三つ葉、クレソン、ミント など)
- トマト
- アロエ
- プラム(すもも)
- 菊花
気のめぐりを良くする食材です。
・ 香りの良い野菜やハーブ(セロリ、せり、三つ葉、クレソン、ミント など)
・ 玉ねぎ、ピーマン、カブ、えんどう豆類(さやえんどう、スナップえんどう、グリーンピース)
・ 陳皮、サンザシ、玫瑰花
・ 柑橘類(レモン、オレンジ、グレープフルーツ など)

「疲労」には『補腎』の食材(山芋、うなぎ、黒ごまなど)が効果的ですが、「疲労感(だるさ)」には『理気』の食材が効果的です。
また、「春の薬膳」でしっかりと血を補えていないと、この時期に『陰虚』の症状が出やすくなります。気温の上昇に伴って空気が乾燥し、汗をかくことで体内の潤いも失われがちです。特に、不眠や寝汗がひどい人は要注意。春に引き続き『補血』『滋陰』の食材や、甘味・酸味のある食材を摂ることが大切です。
甘味・酸味のある食材だと、この時期はプラム(すもも)が旬を迎えますね。プラムには肝気の高ぶりを鎮める作用もあり、初夏におすすめの食材です。
また、旬ではないのに初夏にレモンのスイーツが多く登場するのも、身体が本能的に求めているからかもしれません。ハチミツ漬けにすると甘味+酸味で『肝』の『蔵血』作用を助け、身体に潤いを与える効果があります。国産のレモンは冬〜春の時期に出回り、今の時期に見かけるのは主にアメリカやチリから輸入されたものです。輸入レモンは長距離輸送のため皮表面にポストハーベスト農薬やワックスが使用されています。皮ごと使う場合は流水でよく洗い、必要に応じて野菜用ブラシでこすり洗いをしましょう。
おすすめの薬膳書籍
薬膳を実践していると、よくぶつかるのが「書籍によって効能の記載が違う」という問題です。なぜそんなことが起こるのでしょうか?
それは、薬膳が人間の経験の積み重ねによって発展してきた学問だからです。最初にまとめられた『神農本草経』をはじめ、今日に至るまでのおよそ3,000年(説によっては4,000年)もの間、たくさんの人が薬膳を実践し、自分の身体で効果を感じ取り、解釈し、時には新たな薬膳書を書き記してきました。いわば、今私たちが目にする書籍たちは、中国3,000年の実戦データの集大成と言えます。
そのため、ある本では「寒性」とされている食材が、別の本で「温性」と書かれていたり、「平性」とされているものが実は熱を冷ます作用を持っていたりすることもあります。そんなときは、古代から伝わる複数の書籍を参照することで、その違いの根拠が見えてきます。
こちらの書籍『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』は、まさにそんな場面で頼れる一冊。
この本は、古典を含む複数の薬膳所に記載されている効能を一覧化しており、タイトルのとおり「食品群(穀類、野菜類など)」や「食材名」、「効能(解表、通便など)」から検索できる辞典です。収録されている食材は、なんと1,184種類!迷った時にすぐ調べることができ、薬膳を実践するなら手元に置いておきたい一冊です。
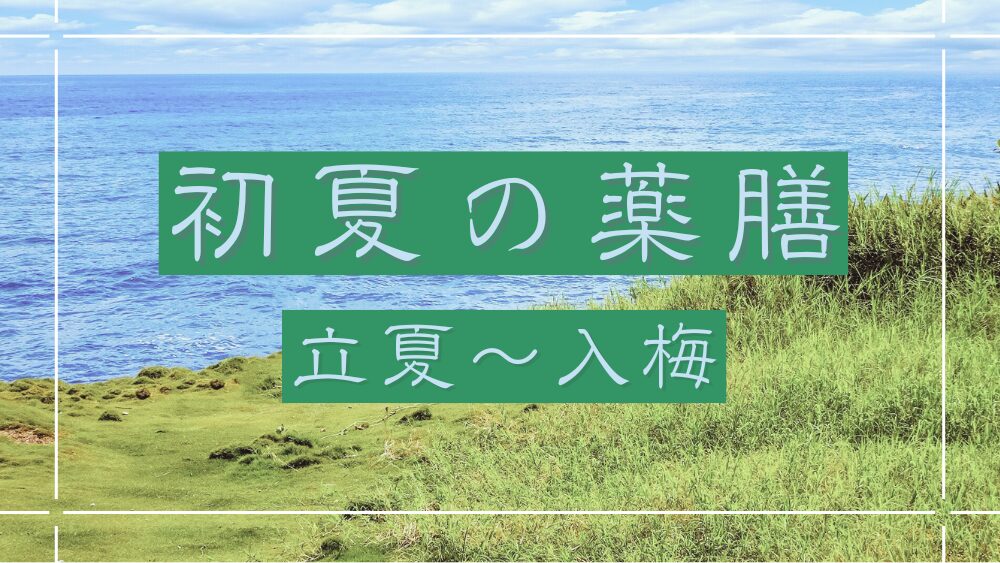

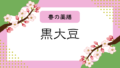

コメント