朝鮮人参の雑学
薬用人参の植物学的分類
私たちが食用と認識しているオレンジ色の人参と薬用人参は、植物学的に全く別の植物です。
★西洋人参(オレンジ色の食用人参)
セリ科:ニンジン属
★朝鮮人参(高麗人参)
ウコギ科:パナクス属
ちなみに「薬用人参」と呼ばれる薬効を目的に使用される人参は、朝鮮人参以外にも以下のような種類があります。
★西洋人参(アメリカ人参)
ウコギ科:パナクス属
北アメリカ原産。鎮静作用が特徴。主に北米で栽培され、その大部分がアジア諸国(特に中国)で消費される。
★田七人参
ウコギ科:パナクス属
中国南部の山岳地帯に自生。血液循環を改善する作用がある。
★シベリア人参
ウコギ科:エレウテロコックス属
東ロシア、中国北部、北海道の一部に自生。別名はエゾウコギ。環境変化やストレスに対する体の適応能力を高める「アダプトゲン効果」が特徴。
日本における歴史
朝鮮人参の原産地は、中国や朝鮮半島とされています。
古代から薬効が重視され、生薬として広く利用されてきました。日本には飛鳥時代に中国から薬用植物として伝わり、滋養強壮などの医薬目的で利用されました。
江戸時代になると、幕府によって栽培が奨励され、全国で栽培が試みられるようになりました。日光や小石川薬園で栽培に成功したのち、幕府は各藩に種子を配布し、広く栽培を奨励したそうです(このため、朝鮮人参は「御種人参(オタネニンジン)」と呼ばれていた)。
この政策で成功した例もありますが(会津藩など)、広範囲での大規模生産には至りませんでした。
原因は栽培に手作業が多く、労力とコストが非常に高いこと。そして収穫までにかなりの時間がかかることです。朝鮮人参は種まきから収穫まで通常4〜6年かかり、この間に根が肥大し、ゆっくりと薬効成分が蓄積されていきます。
ツムラの薬草見本園では、朝鮮人参の展示を見ることができるらしいですね。茨城県阿見町の「ツムラ漢方記念館」に併設されているそうですが、見学できるのは医療従事者のみとのこと。代わりに、バーチャル見学のサイトが用意されています。朝鮮人参の項目はありませんが、とても楽しいサイトです。
『Hello!TUMURAバーチャル漢方記念館』
生薬について
「食」と「薬」の注意点
朝鮮人参は、虚弱体質や体力が低下している『虚証』の人に適した食材です。元気がない、疲れやすい、倦怠感、無気力、食欲不振など、身体が弱った時に食べると効果を発揮します。
しかし、元気が有り余っているような『実証』の人が食べると、むくみ、のぼせ、ほてり、頭痛、鼻血などを引き起こす可能性があります。
「薬膳」と聞くと、朝鮮人参やナツメのような「生薬」(天然自然薬の総称。中医学では「中薬」と呼びます。)を使用した料理を思い浮かべる方も多いのですが、生薬は強い薬効を持つため、使い方次第で毒にも薬にもなり得ます。
まずは身近な場所で購入できる、季節に合わせた食材を食べ、体質の改善をしたい時や体調を崩した時に、はじめて生薬を用いるという流れが良いのではないかと思います。
煎じ薬と顆粒
煎じ薬は、顆粒に比べて、生薬の成分をしっかり摂れる方法とされています。生薬を直接煮出すことで、水に溶けにくい成分や香り成分(精油)まで引き出すことができ、より幅広い成分を取り入れることができます。また、液体なので吸収もスムーズ。顆粒剤も便利ですが、製造過程で一部成分が減少したり、添加物が含まれることがあります。
さらに、煎じ薬は生薬の種類や量を細かく調整できるため、自分の体調に合わせたオーダーメイドのケアが可能なのも魅力。香りや味わいが豊かで、服用時にリラックスできる点も特徴です。準備に手間はかかりますが、より本格的に薬膳を取り入れたい方にはおすすめの方法です。
【おすすめの生薬専門店】草漢堂
朝鮮人参は、古くから薬膳で体力維持や健康サポートに使われてきた中薬です。
「人参湯」はシンプルな組成で、主に「気」を補う薬方。胃腸が弱く、食欲不振や冷え、下痢など消化器系の虚弱が気になるときに用いられます。
「人参栄養湯」は「気」と「血」の両方を補う、より滋養強壮向けの処方。作用が広く、慢性疲労や虚弱体質など全身の回復を促します。
私は以前、同居人が交通事故で手術・入院し、体力が著しく低下したとき、退院後の回復期に朝鮮人参スープを作っていました。野菜スープに「人参栄養湯」を加えて煮出すだけで、体がとても温まりす。
※生薬は体質や体調によって合わない場合があります。初めて取り入れる際や、自己判断が難しい場合は、医師や専門家に相談することをおすすめします。なお、こちらのショップ(草漢堂)では専門家による電話相談も受け付けているので、初めての方も安心です。
【おすすめの煎じ器】文火楽々
煎じ薬を選ぶ場合は、自動煎じ器が断然おすすめです。
通常、生薬を煎じる際は土瓶や耐熱ガラスの鍋で約30分煮出します。煎じ薬は吹きこぼれやすく、また煮詰めすぎを防ぐためにも、火にかけたあとは見張っておく必要があります。
「文火楽々(とろびらんらん)」にはタイマー&火力自動調整機能がついているので、スイッチひとつで最適な煎じ薬が作れるのが魅力。土瓶での煎じと違って、火加減や吹きこぼれを心配する必要がなく、忙しい方でも無理なく続けられます。容量は約1リットルで、1日分の煎じ薬作りにちょうど良いサイズです。個人的には、やかんや土鍋に比べて周辺に漂う「いかにも漢方の香り」が少ないのも高ポイント(笑)。もちろん、煎じ薬だけではなくお茶の煮出しにも活用できます。
ガラス部分が大きくて洗いやすく、お手入れも簡単。万が一割れてしまった場合も、ガラス部分だけ購入できるので安心です。
土瓶や鍋での煎じに疲れてしまった方や、これから始める初心者さんにも安心しておすすめできるアイテムです。
「文火楽々(とろびらんらん)」はAmazonで購入できます!
楽天市場やYahoo!ショッピングでも購入できます!
朝鮮人参の薬膳効能

朝鮮人参には「滋養強壮や疲労回復」の作用があるとされています。
朝鮮人参の主要成分は「ジンセノサイド(Ginsenosides)」と呼ばれる特有のサポニンです。中枢神経に作用し、エネルギー代謝を高めて肉体的疲労を軽減したり、交感神経と副交感神経のバランスを整え自律神経を安定させる効果などが期待できます。
他にも免疫力を高める作用や、血管拡張による血行促進作用など、身体全体の健康維持に多面的な効果を発揮します。特に疲労回復、免疫力向上、自律神経調整など現代人に適した効能が多く、古来から「不老長寿の薬」として珍重されてきました。
おすすめの薬膳書籍
薬膳を実践していると、よくぶつかるのが「書籍によって効能の記載が違う」という問題です。なぜそんなことが起こるのでしょうか?
それは、薬膳が人間の経験の積み重ねによって発展してきた学問だからです。最初にまとめられた『神農本草経』をはじめ、今日に至るまでのおよそ3,000年(説によっては4,000年)もの間、たくさんの人が薬膳を実践し、自分の身体で効果を感じ取り、解釈し、時には新たな薬膳書を書き記してきました。いわば、今私たちが目にする書籍たちは、中国3,000年の実戦データの集大成と言えます。
そのため、ある本では「寒性」とされている食材が、別の本で「温性」と書かれていたり、「平性」とされているものが実は熱を冷ます作用を持っていたりすることもあります。そんなときは、古代から伝わる複数の書籍を参照することで、その違いの根拠が見えてきます。
こちらの書籍『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』は、まさにそんな場面で頼れる一冊。
この本は、古典を含む複数の薬膳所に記載されている効能を一覧化しており、タイトルのとおり「食品群(穀類、野菜類など)」や「食材名」、「効能(解表、通便など)」から検索できる辞典です。収録されている食材は、なんと1,184種類!迷った時にすぐ調べることができ、薬膳を実践するなら手元に置いておきたい一冊です。
|
先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版 新品価格 |
 |
![]()
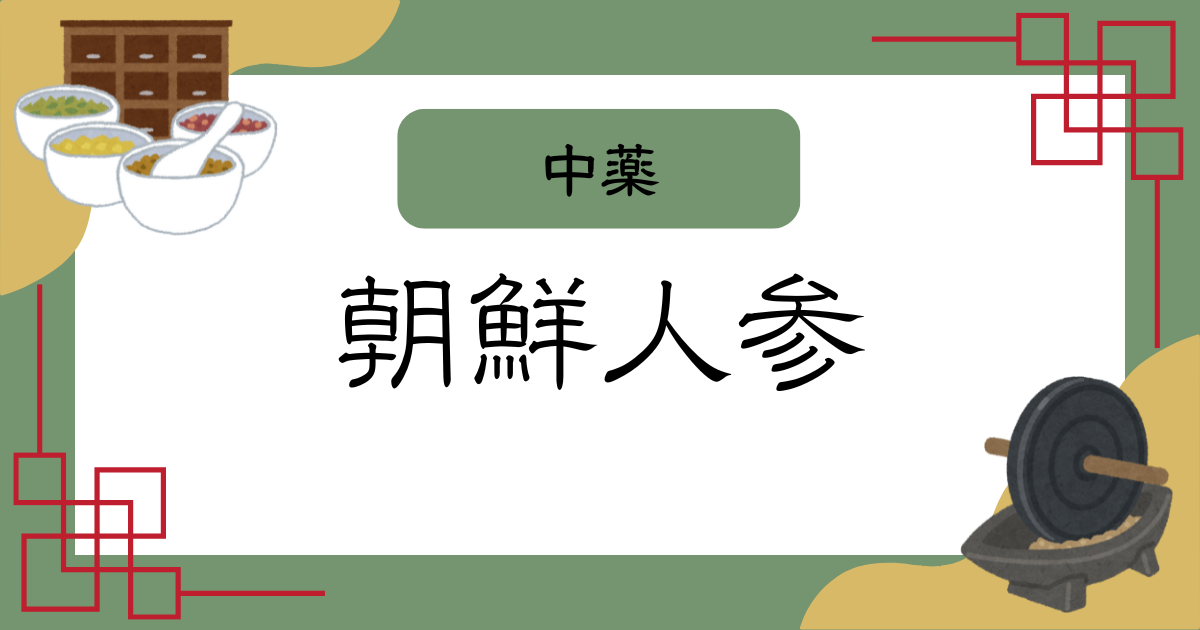



コメント