残暑の薬膳
暦の上ではもう秋ですね。
七十二候では「涼風至(すずかぜいたる)」ーー涼しい風が立ち始める頃とされていますが、実際は今が一年でいちばん暑いとき。福岡でも連日35℃以上を超える猛暑日が続いており、秋の気配は微塵も感じられません。
立秋〜秋分(8月7日〜9月22日)を「残暑の薬膳」としておりますが、立秋があるから区切っているだけで、養生の方法は「夏の薬膳」とほぼ変わりありません。
- 清熱 熱を冷まし、炎症やほてりを鎮めます。
- 解暑 夏特有の『暑邪』による不調をやわらげます。
- 苦味 熱を冷まし、『心気』の高ぶりを鎮めます。
- 安神 精神を安定させます。
- 生津 『津液(潤い)』を生みます。
- 補気 『気』を補います。

『清熱』は「体の内部にこもった熱」に対応する作用。
『解暑』は「環境要因で受けた暑さ(暑邪)」に対応する作用です。
残暑は自分の体質を知るチャンス
ただし、夏の暑さや強い日差しに1ヶ月以上さらされ続けた結果、この時期は徐々に個人差のある不調が現れやすくなってきます。
もともとの体質や、日頃の養生、そして自分の「弱い部分」によって、出てくる症状は人それぞれ。
言い換えれば、「自分の傾向」を見極めるのにちょうど良い時期でもあります。
たとえば私は、「肝気が強く、脾気が弱い」体質です。
そのため「内湿を生みやすい」のですが、カラッとした夏の暑さには比較的強く、「心陽亢進」にさえ気をつけておけば元気に過ごせる傾向にあります(だからといって夏が好きなわけではありませんが笑)。
一方で、同居人は「加齢と過労により腎気が消耗し、陰陽ともに不足しがち」な体質です。
そのため、「陽気が強い夏場は陰が不足しやすく、陰気が強い冬場は陽が不足しやすい」傾向にあり、夏になると陰虚の症状(不眠、寝汗、手足のほてり、口渇、足がつるなど)が出やすくなります。

中医学には、自然界のすべてのものが『陰』と『陽』という二つの相反するエネルギーで成り立ち、互いにバランスをとりながら存在しているという考え方があります。

一方が増えれば、もう一方は自然と減ります。
とはいえ、全体の量は常に相対的に保たれています。
このように、残暑の時期は「その人らしい」不調が現れやすいタイミングです。外がこれだけ暑いので、『清熱』『解暑』は多くの人に必要ですが、加えてーー
- 心陽が亢進しやすい人は、苦味や『安神』作用のある食材を。
- 心陰が消耗している人は、『補血』や『滋陰』作用のある食材を。
- 津液が失われている人は、『生津』と『補気』を中心に。
もちろん、ここでご紹介した症例だけがすべてではありません。たとえば真夏でも冷えを感じるなど、人によって現れる不調はさまざまです。
体調や体質に合わせた「自分専用メンテナンス」を、ぜひ探してみてください。
夏バテ対策
このように個人差はありますが、残暑の時期に共通して多く見られるのが「夏バテ」です。
中医学では、夏に大量の汗をかくことで『津液(体内の水分全般)』が消耗し、『津液』に乗じて『気』も体外へ漏れ出してしまうと考えられています。その結果、『気虚』や『気陰両虚』に陥りやすくなり、これが夏バテの主な要因だとされています。
そのため、発汗による体力の消耗を防ぐケアと、消耗した『気・津液』を補う養生の両方が、夏バテ対策に有効です。
「酸味+甘味」を持つ食材
発汗を抑えるには『収斂(しゅうれん=引き締めて内側に閉じ込める作用)』を持つ「酸味」が効果的です。特に酢やレモンに含まれるクエン酸は、エネルギー代謝をサポートし、疲労回復にも効果的。疲れがたまりやすいこの時期にはぴったりの食材です。わが家では、今の時期はほぼ毎日、小鉢に酢の物やピクルスを添えるようにしています。
また、「夏の薬膳」でもご紹介しましたが、「酸味」に「甘味」を組み合わせることで身体に『津液(潤い)』を生み出す効果が期待できます。梨・ぶどう・りんごなどの旬の果物は「酸味+甘味」を備えているため、今の時期とくにおすすめです。
ただし、果物は「身体を潤す」反面「湿を生みやすい」性質があるので体質によっては注意が必要。私自身は「内湿を発生しやすい」体質のため、普段は控えめにしています。
『補気』『健脾』の食材
夏バテ対策には『気』を補う『補気』の食材も欠かせません。
ただし、『気』を十分に生み出すためには『気血化生の源』である『脾』が健やかに働いていることが大前提です。いくら良い食材を摂っても、『脾』がうまく消化吸収できなければ意味がありません(※詳しくは「梅雨の薬膳」をご覧ください)。
『脾』は冷えと水分に弱いため、夏に冷たいものを食べ過ぎたり、エアコンに長時間あたったりした人は、『脾』の不調があらわれやすくなる頃です。
お腹の調子が悪い方、なんとなくだるい方、『湿』の症状(水太り、むくみ、重だるさなど)が気になる方は、『脾』の働きを弱める食材を控え、『健脾』作用のある食材を意識して取り入れてみてください。
- 甘いもの
- 冷たいもの
- 脂っこいもの
- 味が濃いもの
- アルコール類
🌾 穀類(玄米、うるち米、もち米、あわ、きび、ひえ、米麹)
🍠 芋類(さつまいも、じゃがいも、山芋)
🫘 豆類(いんげん豆、黒豆、大豆)
🥜 種実類(アーモンド、栗、棗、蓮の実、菱の実、落花生)
🥬 野菜類(枝豆、おくら、小松菜、生姜、チンゲンサイ、とうもろこし、なす、人参、れんこん)
🍎 果物(干し柿、ライチ、りんご)
🐟️ 魚介類(イワシ、スズキ、鯛、ハモ、鰤)
これらの食材は、消化にやさしい状態(おかゆやスープなど)で摂るのがおすすめです。疲れた『脾』をいたわりながら、ゆっくり整えていきましょう
ぬるぬる・ネバネバの食材
ぬるぬる・ネバネバの食材も、夏バテ対策に有効です。
胃腸にやさしく、『気』を補い、身体を潤す働きがあるとされています。
オクラ、モロヘイヤ、ツルムラサキ、長芋、納豆、新里芋など
ただし、これらの食材は身体に潤いを与える反面「湿を生みやすい」性質があります。
すでに『湿』の症状が出ている方は、『利湿(りしつ)』や『滲湿(しんしつ)』の食材(ハト麦・とうもろこし・小豆・枝豆・緑豆など)と組み合わせて取り入れてください。
夏・残暑の養生には「睡眠」を
「菊花」の記事でもご紹介したように、『心』は睡眠と深く関係しています。『心』に不調があると睡眠に支障をきたし、逆に睡眠が不足すると『心』に由来する不調(神経ピリピリ、不眠、動悸など)が出やすくなります。
「夏・残暑の薬膳」では、食養生も大事ですが、まずはしっかりと休むこと、特に睡眠が何より重要。目を閉じて視覚からの情報を遮るだけでも、脳や神経の回復につながります。
とくに、一日のなかで最も陽気が高まる正午に『心気』を休めると効果的とされており、15〜20分ほど昼寝をするのが夏の養生としておすすめです。
短い睡眠におすすめのアイピロー
短時間でも十分な休息が取れるよう、私はアイピローを活用しています。昼食後にアイピローをのせて15分ほど目を閉じるだけで、『気』が整い、回復するのを感じます。
私が使っているのは、乾燥ラベンダーが配合された「Yoga Labo」さんのクリスタルアイピロー。ラベンダーには『心』が蔵する『神(しん=精神活動全般)』を鎮静する作用があるとされており、リラックス効果に加えて、血圧降下や自然な眠りのサポートも期待できます。
市販されているラベンダー入りアイピローの多くは玄米や小豆などの天然素材が詰められていて、温めて使うと気持ちいいのですが…保管方法が面倒くさいため、ズボラな私には使いこなせません(笑)。
「Yoga Labo」さんのアイピローは水晶のさざれ石(クリスタル)と乾燥ラベンダーが使われており、ほど良い重みが魅力です。お手入れはたまにシルク素材のカバーを洗濯するくらいでOK。私はかれこれ10年ほど愛用しています。
(※販売サイトはこちら →Yoga Labo公式サイト)
おすすめの薬膳書籍
薬膳を実践していると、よくぶつかるのが「書籍によって効能の記載が違う」という問題です。なぜそんなことが起こるのでしょうか?
それは、薬膳が人間の経験の積み重ねによって発展してきた学問だからです。最初にまとめられた『神農本草経』をはじめ、今日に至るまでのおよそ3,000年(説によっては4,000年)もの間、たくさんの人が薬膳を実践し、自分の身体で効果を感じ取り、解釈し、時には新たな薬膳書を書き記してきました。いわば、今私たちが目にする書籍たちは、中国3,000年の実戦データの集大成と言えます。
そのため、ある本では「寒性」とされている食材が、別の本で「温性」と書かれていたり、「平性」とされているものが実は熱を冷ます作用を持っていたりすることもあります。そんなときは、古代から伝わる複数の書籍を参照することで、その違いの根拠が見えてきます。
こちらの書籍『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』は、まさにそんな場面で頼れる一冊。
この本は、古典を含む複数の薬膳所に記載されている効能を一覧化しており、タイトルのとおり「食品群(穀類、野菜類など)」や「食材名」、「効能(解表、通便など)」から検索できる辞典です。収録されている食材は、なんと1,184種類!迷った時にすぐ調べることができ、薬膳を実践するなら手元に置いておきたい一冊です。
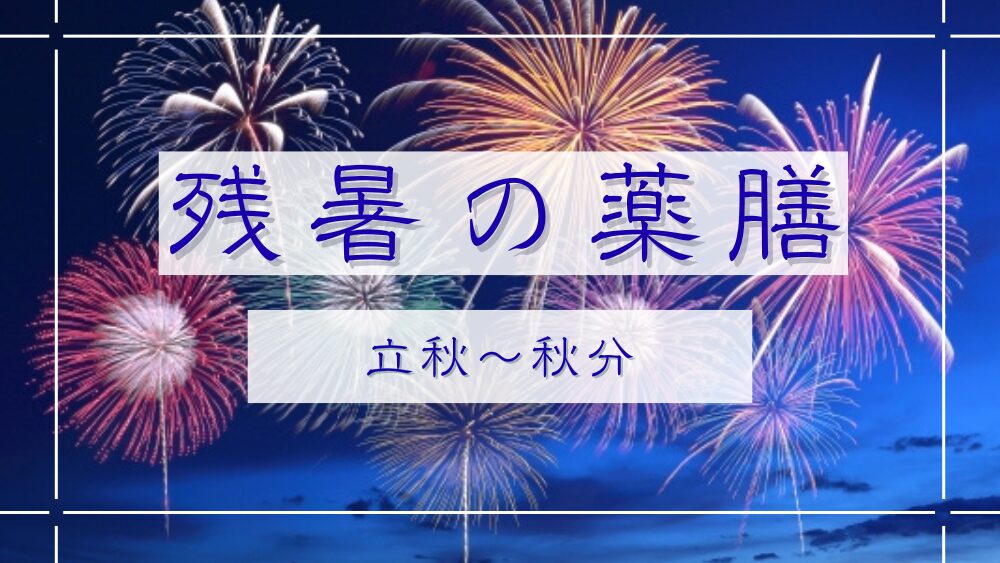



コメント