夏の到来と博多祇園山笠「追い山笠」
本日午前4時59分から、7つの「舁き山笠(かきやま)」が町を駆け抜ける「追い山笠(おいやま)」が行われ、15日間続いた福岡最大の祭り「博多祇園山笠」はついにフィナーレを迎えました。
福岡では、「追い山笠が終わると梅雨が明ける(=夏が来る)」という言い回しが広く知られています。これは「追い山笠」の終了が、ちょうど梅雨明けや本格的な夏の到来と重なることが多いために生まれたものです。
実際の梅雨明けのタイミングは年によって異なり、必ずしも追い山の直後に梅雨が明けるわけではありません。統計的には、追い山の直後3日以内に梅雨が明けるのは約3割、1週間以内だと約6割。今年のように、追い山より前に梅雨が明けることも珍しくありません。
それでも、「山笠が終わると夏が来る」という感覚は、福岡の人々にとって季節の節目を告げる大切な言葉として、今も定着しています。
夏の養生ポイント①
『暑邪』と『火邪』
これまでのブログでもたびたび登場している中医学のキーワードに、『六淫の邪気(風・寒・暑・湿・燥・火)』があります。これらは本来『六気』と呼ばれる自然界の正常な気候ですが、適応範囲を超えて人体に悪影響を及ぼすようになると『邪気』となります。
このうち、温熱系の邪気は『暑』と『火』の2つ存在していますね。それぞれの特徴は次の通りです。
🔥『暑邪(しょじゃ)』
主に夏の高温や発汗過多など、「暑さ」による体調不良を指します。
代表的な症状は、発熱・口渇・多汗・倦怠感・脱力感など。夏バテや熱中症の初期症状に近いものです。
🔥『火邪(かじゃ)』
暑邪よりもさらに激しい熱症状を指します。
体内で「炎が燃え上がる」ような状態で、炎症・腫れ・痛み・出血(吐血・血尿・血便など)を伴うのが特徴です。
火邪は暑邪と同様に高温環境で発生しやすいですが、病態はより重く、激しい症状が出る傾向があります。
🔥オマケ『熱邪(ねつじゃ)』
火邪と暑邪はどちらも温熱性の外邪であり、まとめて「熱邪」と総称されることもあります。
また、「火邪=熱邪」と同義で使われることもありますが、厳密には火邪のほうが、より激しい症状に使われる傾向があります。
おすすめの薬膳食材:熱を冷ますもの
外から侵入する『暑邪』には、『清熱(せいねつ)』『解暑(げしょ)』の働きをもつ食材がおすすめです。
「熱を冷ます=冷たいものを食べれば良い」と思われがちですが、それで冷えるのはほんの一瞬。しかも、いちばん冷やしてはいけない『脾(ひ)』を直撃してしまい、かえって体調を崩す原因になります。
以下の食材は、常温や温かい状態で食べても、体内の余分な熱を冷ます作用があるとされます。
🍉 ウリ類(きゅうり、冬瓜、ゴーヤ、スイカ、メロン)
🍆 なす、もやし、ズッキーニ、アスパラガス、ツルムラサキ、空芯菜、チンゲンサイ、クレソン、ミント、レタス、アロエ、さとうきび
🍌 パイナップル、バナナ、キウイ、梨
🫘 ハトムギ、菱の実、緑豆、豆腐、こんにゃく
🦀 カニ、昆布やわかめなどの海藻類
🍵 菊花茶、緑茶
🍉 ウリ類(ゴーヤ、スイカ、メロン)
🍅 トマト
🍌 バナナ、パパイヤ、レモン
🌺 ココナッツ、ハイビスカス
🫘 菱の実、緑豆
夏の養生ポイント②
夏は心陽が亢進しやすい季節
五臓のうち『心(しん)』は、五行で「火」、五季では「夏」に属し、夏の暑さに影響を受けやすいと考えられています。
| 五行 | 五臓 | 五季 | 五液 |
| 木 | 肝 | 春 | 涙 |
| 火 | 心 | 夏 | 汗 |
| 土 | 脾 | 土用または長夏 | 涎(よだれ) |
| 金 | 肺 | 秋 | 涕(はなみず) |
| 水 | 腎 | 冬 | 唾(だえき) |
夏は一年の中で最も“陽気”が高まる季節。
「早春の薬膳」でもお伝えしたように、人間も自然の一部なので、自然界の陽気が高まると人体の陽気も活発になります。
五臓のうち、とくに『肝』と『心』の陽気は亢進しやすい(過剰になりやすい)という性質があり、夏は『心陽亢進』の状態に陥りやすいとされています。
中医学の『心』とは
中医学における『心(しん)』とは、西洋医学でいう単なる「心臓」ではありません。
生命活動の中心を担う、非常に重要な臓腑として位置づけられています。

『心』には『主血(しゅけつ)』と『蔵神(ぞうしん)』という働きがあります
『主血』
『主血』とは、ポンプ機能と血脈のコントロールによって、全身に血液を循環させる働きです。
『蔵神』
『神(しん)』とは、意識・思考・感情・睡眠などを含む、精神活動全般を指します。
中医学では『心が神を蔵する』とされており、現代医学でいう「脳」や「自律神経」に通じる広い役割を担っていると考えられています。
実際、血のめぐりと自律神経は深く関わっており、交感神経は血管を収縮させ、副交感神経は血管を拡張させます。このバランスが乱れると血流が悪くなり、自律神経の不調を招きやすくなります。

ということは、血のめぐりを良くすれば自律神経も整うということだね!
『心』の不調による症状
『心陽亢進』
『心陽亢進』とは、『心』の働きや熱が過剰になっている状態です。
『主血』のポンプ機能が過剰になると、動機や息切れなどの症状が現れやすくなります。
『蔵神』の働き(=精神活動)が過度に高まると(つまり脳がフル回転しているような状態)、興奮状態が続き、交感神経が優位になって睡眠を妨げる原因になります。
- 動悸、息切れ
- 顔面紅潮
- 興奮や焦燥感
- 不眠、多夢
また、『肝』と『心』はお互いに影響を及ぼしやすい関係にあるため、どちらかが亢進すると、もう一方も亢進しやすくなります。『心陽亢進』のときには肝陽も亢進し、イライラ、頭痛、目の充血といった症状も現れやすくなります。
『心陰虚』
上の五行の表から分かるように、『心』の『五液』は『汗』。つまり『心』は汗と深い関係があります。
夏は発汗量が多くなり、体内の『津液(水分)』が消耗します。『津液』と『血』は互いに補い合う関係にあるため、『津液』が減ると『血』も不足し、結果として『陰液』全体が不足してしまいます。これを『陰虚(いんきょ)』と呼び、どの臓腑でも起こりうるのですが、夏はとくに『心』の陰液が不足しやすく、『心陰虚』になりやすい傾向があります。
身体の潤いが不足すると体内に熱がこもりやすくなるため、のぼせや寝汗、不眠などの不調があらわれやすくなります。
- 口の乾き
- のぼせ感
- 手のひらや足の裏のほてり
- 寝汗
- 不眠
- イライラ

『心陽亢進』の不眠は「ギンギン目が冴えている」状態なのに対し、『心陰虚』の不眠は「ほてりで眠れない、寝苦しい」状態です。
夏の『心』の不調に対するおすすめの薬膳食材
おすすめの薬膳食材:心陽を鎮静するもの
心陽を鎮めるには「苦味」を持つ食材が効果的です。
苦味には主に「熱を冷ます」作用と「余分なものを排出し引き締める」作用があり、体内の余分な熱や水分、毒素、老廃物などを排出して『血』をキレイに保つ働きも期待できます。
ただし、苦味を持つ食材は胃に負担をかけやすいため、胃が弱っている時や空腹時には控えめに。
🥒 アスパラガス、アロエ、ゴーヤ、モロヘイヤ
🍊 グレープフルーツ
🍵 緑茶、菊花茶、烏龍茶、コーヒー
症状が「不眠」の場合、緑茶・烏龍茶・コーヒーはカフェインによる覚醒作用で逆効果となる場合があります。夜の時間帯には、カフェインレスの菊花茶がおすすめ。
おすすめの薬膳食材:心を養うもの
眠れないときや、気持ちがそわそわして落ち着かないときには、『心』をやさしく補い、精神を落ち着ける『安神(あんじん)』の働きを持つ食材がおすすめです。
🌾 小麦
🫘 アーモンド、蓮の実、百合根
🦪 イワシ、牡蠣、シジミ
🫖 ジャスミン茶
棗(なつめ)や龍眼肉(りゅうがんにく)なども『安神』の働きをもつ食材ですが、いずれも温性なので、夏の養生には不向きとされます。熱を冷ます作用のある緑茶や烏龍茶と合わせて摂るのがおすすめ。
おすすめの薬膳食材:身体を潤すもの
夏の薬膳では、汗で失う水分をしっかり補うことが大切です。
この場合、『補陰』『滋陰』のような「陰液全体を補う食材」よりも、まずは体内の水分=『津液』を補う『生津(せいしん)』の働きを持つ食材がおすすめです。
🥛 豆腐、豆乳、牛乳、ヨーグルト
🥒 アスパラガス、オクラ、きゅうり、冬瓜、トマト、ズッキーニ
🍑 いちじく、梅、梨、桃、すもも、ライチ、りんご、マンゴー、レモン、シークワーサー
🥥 ココナッツ、棗(なつめ)、さとうきび
また、「苦味」と同様に、「酸味」にも引き締める作用があります。
ただし苦味が「出す」性質をもつのに対し、酸味は「内側に入れて閉じ込める(収斂)」性質があり、発汗を抑える作用があります。
補う作用をもつ「甘味」と一緒に摂ることで潤いが生まれるため、「甘味+酸味」を兼ねた果物や、梅・レモンを氷砂糖に漬けた自家製シロップなどもおすすめです。
これらはクエン酸による疲労回復効果も期待でき、夏バテ予防にもぴったりです。
おすすめの薬膳食材:気を補うもの
汗と一緒に『気』も流れ出てしまうと、だるさや食欲不振といった夏バテの原因になります。そのため、失った『気』を補う『補気』の食材も、積極的に摂り入れたいところです。
🌾 甘酒、玄米、うるち米、もち米
🍠 さつまいも、じゃがいも、山芋
🫘 大豆、棗(なつめ)、カカオ、菱の実
🥑 枝豆、アスパラガス、カボチャ、さやいんげん、とうもろこし、アボカド
🍑 桃
🦐 イワシ、うなぎ、えび、タコ、鮭、マグロ
🥚 牛肉、豚肉、鶏肉、たまご
おすすめの薬膳書籍
薬膳を実践していると、よくぶつかるのが「書籍によって効能の記載が違う」という問題です。なぜそんなことが起こるのでしょうか?
それは、薬膳が人間の経験の積み重ねによって発展してきた学問だからです。最初にまとめられた『神農本草経』をはじめ、今日に至るまでのおよそ3,000年(説によっては4,000年)もの間、たくさんの人が薬膳を実践し、自分の身体で効果を感じ取り、解釈し、時には新たな薬膳書を書き記してきました。いわば、今私たちが目にする書籍たちは、中国3,000年の実戦データの集大成と言えます。
そのため、ある本では「寒性」とされている食材が、別の本で「温性」と書かれていたり、「平性」とされているものが実は熱を冷ます作用を持っていたりすることもあります。そんなときは、古代から伝わる複数の書籍を参照することで、その違いの根拠が見えてきます。
こちらの書籍『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』は、まさにそんな場面で頼れる一冊。
この本は、古典を含む複数の薬膳所に記載されている効能を一覧化しており、タイトルのとおり「食品群(穀類、野菜類など)」や「食材名」、「効能(解表、通便など)」から検索できる辞典です。収録されている食材は、なんと1,184種類!迷った時にすぐ調べることができ、薬膳を実践するなら手元に置いておきたい一冊です。



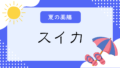
コメント