このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。
2025年3月20日(春分)から5月5日(立夏)までは、「春の薬膳」としてご案内しています。
中医学『以臓補臓』
中医学には、「身体の不調な部位を治すには、その部位と同じ、または似た形の食材を摂取すると良い」とする考え方があり、これを「同物同治(どうぶつどうち)」と呼びます。
例① 脳に似た形の胡桃(くるみ)が、脳の働きを高めるとされる。
例② 靱帯を損傷した場合、牛スジを食べることで回復が早まると考えられる。
この考え方は、自然界との調和を重んじる「整体観念」にも通じています。
特に動物の臓器には、その部位特有の栄養素が含まれており、それが人間の同じ部位に作用すると考えられています。そのため、中国では精肉以上に副生物(内臓など)が重視されています。
「同物同治」の中でも、臓器に特化したこの考え方は「以臓補臓(いぞうほぞう)」と呼ばれます。例えば、肝臓が弱っている場合には動物の肝臓(レバー)を食べることで肝の働きを補います。
春は肝への負担が増えるため、レバーはおすすめの食材です。
アルコールと『肝』
西洋医学の観点から見る『肝臓』と同様に、中医学の観点から見る『肝』も、アルコールと深くかかわっています。私のような酒飲みには、もってこいの食材ですね。
中医学ではアルコールを「熱が多い水分」と捉えます。適量であれば血行促進やリラックス効果がありますが、過剰摂取すると「酒毒」となり、体に悪影響を及ぼします。
アルコールは脾胃で吸収された後、『肝』に送られて解毒が行われます。しかし『肝』の働きが弱っていると、うまく処理できず、体内に余分な『湿』と『熱』が生じてしまいます。
発生した『湿熱邪』には『清熱解毒』の食材(ウコン、しじみ、梨など)が効果的ですが、まずは発生させないために日頃から『肝』を養生し、解毒機能を正常に働かせることが重要です。
おつまみとしての鶏レバーの適量
栄養学の観点から見ても、レバーにはビタミンA、ビタミンB群(特にB12)、鉄分、葉酸など、肝臓の機能を助ける栄養素が豊富に含まれています。とくにアルコールの代謝にはビタミンB群が重要で、レバーを食べることでその補給が期待できます。
ただし、過剰摂取はビタミンAの過剰症やカロリー過多につながる可能性があるため、適量を心がけることが大切です。
私の場合、週に2〜3日、一度に2〜3合ほどのお酒を嗜みますが、その程度の飲酒であれば、レバーは1回につき20〜30gを、週に1〜2回程度がちょうど良いと感じています。焼鳥のレバー串だと、一般的に1本約30g程度です。
「焼とりの八兵衛」のレバー串
日本で一般的に食べられているのは牛・豚・鶏のレバーですが、飲酒対策として食べるには鶏レバーがおすすめです。100gあたり約100kcalと低カロリーで消化しやすいため、飲酒時の負担が少なく済みます。
先週末の宅飲みでは、同居人のために「焼とりの八兵衛」のレバー串を用意しました。「ららぽーと福岡店」はテイクアウト専門店です。八兵衛さんのレバー串はテイクアウトでも美味しいので、同居人のお気に入りです。
・きも(塩)195円
・きも(たれ)195円
・砂ずり 192円 × 2本
・つくね 280円 × 2本
・よつみ 230円 × 2本
・えんどう豆の串揚げ 230円
・かしわおにぎり4個 450円
合計 2,474円
店舗情報
住所 福岡県福岡市博多区那珂6-23-1
定休日 施設に準ずる
営業時間 10:00〜21:00
※変更となる場合がございますので、ご来店前に店舗情報をご確認ください。

【酒飲みにおすすめ!】せんべろメーカー
温めるのに使用しているのはLITHONの「せんべろメーカー」です。焼鳥はもちろん、テイクアウトした天ぷらやフライでもサックサクに温めることが出来ますし、おでんや熱燗も楽しむことができます。見た目が少しチープだったので、オモチャ感覚で購入しましたが、今では我が家の宅飲みに欠かせない存在になっています。本体は拭くだけ、備品は洗うだけで、手入れもとても簡単です。
Amazonで購入できるリンクを貼っておきますので、ぜひ一度お試しください!
楽天やYahoo!ショッピングでも購入できます
好き嫌いの話
ここまで書いておきながら、私はレバーが大の苦手です…。どのように調理されていても食べることができません。
レバーに限らず、私はかなり好き嫌いが激しい方だと思います。福岡に住んでいるのに、モツ鍋も明太子もごまサバも苦手ですし、豚骨ラーメンや水炊きも好んでは食べません。
若い頃は「まだ本当に美味しいものに出会っていないだけだよ、この店のなら絶対に食べられるよ!」とあちこち連れ回されましたが、どこで食べようが苦手なものは苦手でした。
こんなに好き嫌いが激しくても薬膳が実践できるのか疑問を持たれることがありますが、むしろ苦手だからこそ薬膳に助けられている部分が大いにあります。レバーが苦手でも、いちごや乾椎茸など他の食材で『肝』を養うなど、自分が美味しく食べられるものの中から食材を選んで、身体のバランスを整えることができています。
逆にいくら薬膳的に効果の高い体質に合った食材でも、美味しいと思わなければ食べませんし、同居人にも無理強いしません。
佐野未央子さんの「日日べんとう 1巻」に、「心からうまい!と思えない物を食べても栄養になると思えない」「食べなければならないと思いながら食べるのは、ストレスを食べるのと同じこと」という内容のセリフが登場しますが、大いに共感しています。好き嫌いは無いに越したことありませんが、無理して食べる食事はストレスそのものです。食事は美味しく食べられるのが一番だと思っています。
鶏レバーの薬膳効能

鶏レバーには「特に小児の基礎体力を養う」作用があるとされています。
レバーには『肝』を養い、『血』を補う効果があります。
「春の薬膳」で解説したように、『肝』には血を貯蔵し、必要に応じて身体の各部分に供給する『蔵血』という働きがあります。そして「人参」で解説したように、『肝』の『五主』は筋、『五官』は目なので、『蔵血』の働きが正常であれば、目や筋肉に血が行き渡り、目の疲れや乾燥、視力低下(例えば夜盲症)などの改善、筋肉のしびれやこむら返り、筋力低下などの症状が軽減されます。
もちろん目や筋に限らず、血を補うことは貧血を改善し、皮膚や髪の健康を保ち、月経不順や出血量不足、更年期症状などの女性特有の問題にも効果的です。
また、『肝』を養うことで気血を全身にめぐらせる『疏泄』の働きも良くなり、気血がスムーズに流れることでイライラやストレスが緩和され、精神的な安定にもつながります。
牛や豚のレバーも肝や血を補う作用がありますが、中医学では目的に応じて適切な種類のレバーを選ぶことが推奨されています。
★牛レバー:肝に特化しており、目の疾患改善や血液補充に優れています。
★豚レバー:脾胃を補い、消化機能や気の強化に役立ちます。
★鶏レバー:唯一「腎」を補う作用があるため、生命力や基礎的な体力強化に特化しています。
鶏レバーは身体を温める「温性」の食材で、冷え性や体力不足に悩む人に向いています。薬膳では他の腎精チャージ食材(山芋、黒豆など)と組み合わせて、体力作りを目的とした煮込み料理に使われることもあります。
豚や牛のレバーほどクセがなく、低カロリーで消化しやすいため、小児や幼児にも適した食材とされています。ビタミンA、ビタミンB群(特にB12)、鉄分、葉酸が豊富で、特に鉄分は「ヘム鉄」で吸収率が高い(約20%)ため、成長期の貧血予防や基礎体力作り、免疫力向上などに効果的です。給食によく登場するのも納得ですね。給食では児童にも食べやすいよう、竜田揚げなど臭みを抑える調理法が工夫されています。
ただしビタミンAは脂溶性ビタミンであり、過剰摂取すると健康被害(頭痛や吐き気など)を引き起こす可能性があるため、小児の場合でも適量を守ることが重要です。
おすすめの薬膳書籍
薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。
複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。
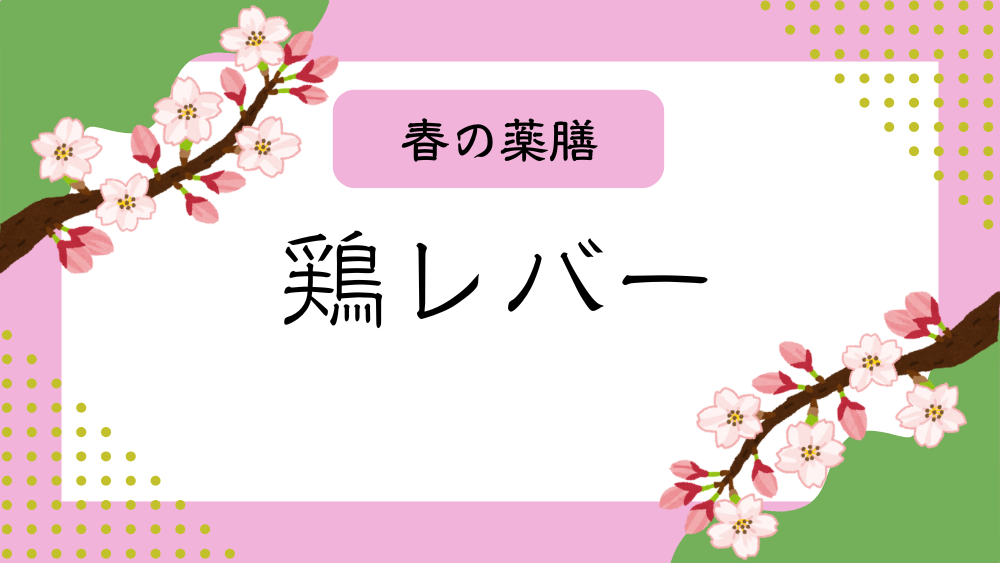




コメント