このブログでは、季節に応じた薬膳食材をご紹介しています。
2025年3月20日(春分)〜5月5日(立夏)の期間を『春の薬膳』としてご案内しています。
イースター
今日はイースター。
「春分の日の後の、最初の満月の次の日曜日」に祝われる、キリスト教のイベントです。イエス・キリストが十字架で処刑され、3日後に復活した奇跡を記念する日で、日本語では「復活祭」とも呼ばれます。
キリスト教の文化圏では、春を象徴するゲルマン神話の女神「エオストレ(Eoster)」とイエスの復活のイメージ(新しい命、再生、希望など)が重なることから「イースター(Easter)」と呼ばれるようになったとも言われています(諸説あり)。そのため、イースターには春の訪れを祝う意味も含まれています。
この日は教会でミサに参加し、家族でご馳走を囲む習慣があります。子孫繁栄の象徴とされるウサギの「イースターバニー」を飾り、子どもたちはカラフルにペイントされた「イースターエッグ」で遊びます。これは春の訪れに感謝したウサギが女神エオストレに美しく装飾したたまごを贈ったという言い伝えに由来するとされています(これも諸説あり)。庭に隠された「イースターエッグ」を誰が一番多く見つけられるかを競う「エッグ・ハント」では、優勝者した子どもにお菓子が入ったエッグケースが贈られます。
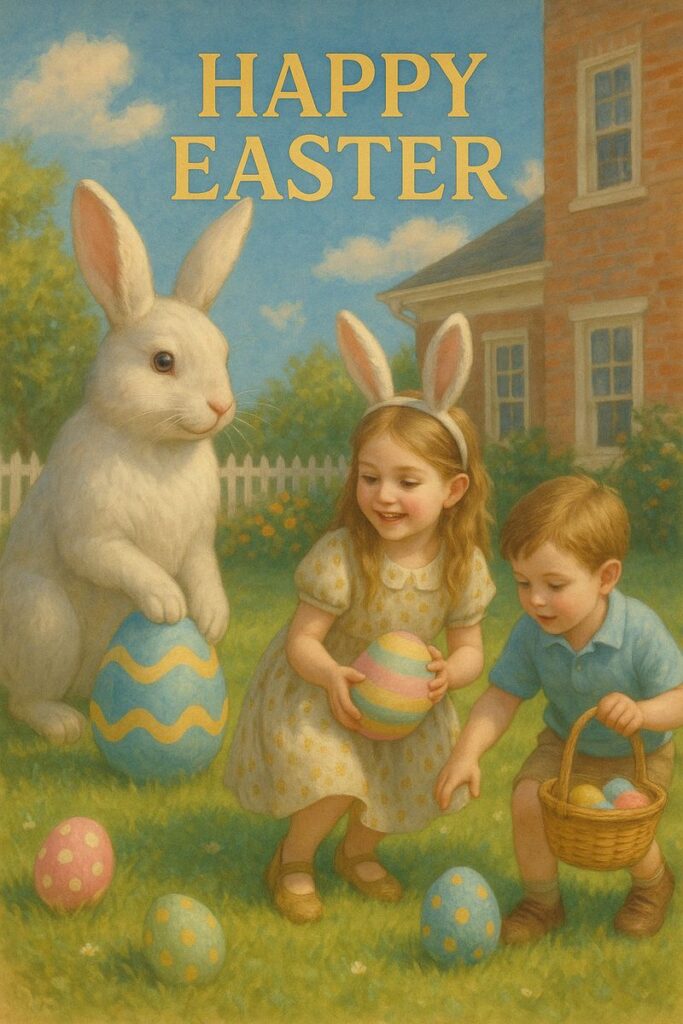
たまごの雑学
今日はイースターにちなんで、「たまご」の話を。
実際、たまごの旬は春と言われています。もともと原種に近い鶏や、自然に近い飼育環境の鶏は、春の繁殖期にしか産卵しませんでした。今では品種改良や飼育環境の工夫で一年中産卵するようになりましたが、春は鶏の体調が整いやすく、「春卵は美味」と言われています。
たまごの賞味期限
日本卵業協会では、日本のたまごの賞味期限を「産卵後1週間以内にパックし、パック後2週間以内」と定めています。つまり、産卵から数えておよそ3週間ということになります。
ただし、これは「夏場に生で食べること」を前提に設定されたもの。実際には、気温が10℃前後と低い冬の時期であれば、産卵から57日間(およそ2カ月近く)まで生食が可能とされています。
しかもこの基準は「生で食べること」が前提なので、賞味期限を過ぎていても異常がなければ、加熱調理して食べることができます。市販のパックにも、たいてい次のような注意書きが記載されています。
賞味期限経過後、及び、殻にヒビの入った卵を飲食に供する際は、なるべく早めに、十分に加熱調理してお召し上がり下さい
つまり、「賞味期限を過ぎても、加熱調理すれば食べられる」ということは、しっかり明記されているのです。
ただし、保存は必ず「25℃以下」が条件です。産卵から自宅の冷蔵庫に入れるまでのあいだに、25℃以上の環境に置かれていた可能性がある場合は、賞味期限内に食べきるのが安心です。
たまごと食中毒
たまごに付着している代表的な食中毒菌といえばサルモネラ菌です。日本のたまごはとても安全ですが、それでも取り扱いには注意が必要です。
サルモネラ菌は36℃の環境に1日放置するだけで増殖すると言われており、夏場の常温放置は特に危険です。熱に弱いので75℃で1分以上加熱すれば死滅しますが、夏の暑い日は、温泉玉子や半熟オムレツ、パンを卵液に長時間浸すフレンチトーストなど、食中毒予防の観点から控えるのが無難かもしれません。
たまごの保存方法
冷蔵庫で保存する場合、たまご専用のポケットに入れておくと、ドアの開け閉めの際に殻にひびが入ってしまうことがあるので、買ってきたパックごと尖ったほうを下にして保存するのがおすすめです。尖ったほうには空気の入る「気室」があるため、こちらを下にすることで鮮度が長持ちします。
ゆでたまごは日持ちしにくいので要注意です。生たまごにはリゾチームという酵素に菌の繁殖を防ぐ効果があるのですが、加熱すると壊れてしまうため、菌が繁殖しやすくなります。
殻付き…3日程度
殻むき…1日程度
調味液に漬け込んだ味付け玉子…2〜3日程度 ※夏場のお弁当には不向き
たまごは、加熱することを前提とすれば、生のまま冷凍保存も可能です。使うときは殻を剥き、凍ったまま調理します。扱いやすいので袋煮などを作る際に便利ですし、半分に切ってフライパンで焼くと、小さな目玉焼きを作ることができます。
たまごのレシピとおすすめ商品
冷凍たまごの活用レシピ

① 油揚げを湯通しして開く。
② 鍋に「飲んでおいしい」くらいに味付けしただし汁を沸かす。
※私は「くばらあごだしつゆ」50cc、水500cc、みりん大さじ1の割合です。
③ 冷凍保存しておいたたまごを水に浸け、殻をむいて半分に切る。
④ ①の油揚げに③を入れ、袋を閉じる。

温泉玉子と科学
温泉たまごは、たまごの持つタンパク質の違いをうまく利用した調理方法です。たまごの中でも、卵白と卵黄では固まる温度が違うため、それを逆手に取ることで、あの絶妙なとろとろ加減が生まれます。
卵白の特徴
・水分が多く、タンパク質は比較的少なめ
・62℃から固まり始め、完全に固まるのは80℃近く
卵黄の特徴
・タンパク質が多く、水分は少なめ
・65℃〜70℃で固まる
このため、65〜70℃で加熱すれば「卵白はぷるぷるで卵黄よりやわらかい」「卵黄は詰まっていて濃厚、卵白より固い」という絶妙なバランスが実現します。

温泉玉子のレシピ
5年ほど前に低温調理器を購入して以来、月に1〜2度は温泉玉子を作り続けています。
ひとつだけ注意するとすれば、たまごの初期温度。たとえば室温(今現在は20℃前後)と冷蔵庫から出したて(5℃前後)ではスタート時点で15℃もの差があります。この違いによって、目標温度に到達するまでの時間が変わってくるので、調整が必要になります。
また、鍋に入れるたまごの数が多いと投入直後に水温が下がり、目標温度まで復帰するのに余分な時間がかかります。私はいつも1度に5〜6個作りますが、1パックぶん(10個)くらいなら水温低下に影響ないと思います。

① 低温調理器を65〜70度に設定する。
② 冷蔵庫から出したてのたまごを、おたまで1個ずつ湯に沈める。
③ 30分後に取り出し、流水で粗熱を取る。
※ 殻付きのまま冷蔵庫で2〜3日保存できますが、冷やすとやや硬くなります(それはそれで美味しい)。
好みの固まり具合は人それぞれなので、何度も作ってみて自分のレシピを作り上げるしかありません。私は68℃のかためを味噌汁やスープに落として食べるのが好きですし、同居人は65℃のゆるめを玉子かけご飯にして食べるのが好きです。
おすすめの低温調理器
私が使用しているのは「MODERN DECO(株式会社De-Dream)」の「スリムデザイン 低温調理器」ですが、現在は販売されていないようです。次に買い替えるとしたら、【アイリスオーヤマ】LTC-04と決めています。
低温調理器を使う際は、ある程度の深さがある鍋が必要になりますが、「LTC-04」なら大丈夫。独自の「ギザギザクリップ」を搭載しているので、浅めの鍋から深めの鍋まで、さまざまなサイズにしっかり対応してくれます(※使用可能な鍋の目安:深さ10cm以上・内径20cm以上・容量15L以下)。
温度は25〜95℃まで、時間は1分〜99時間59分まで設定可能。低温でじっくり長時間加熱ができるので、豚の角煮はもちろん、骨まで食べられるいわしの煮物など、手間のかかる料理も簡単に楽しめます。
さらに、防水性能は「IPX7」相当。水に落としても壊れにくい安心仕様で、日々の調理にも安心して使えます。「丸洗いできる」とされていますが、基本的に水しか使わないため、サッと拭くだけでお手入れも簡単です。
たまごの薬膳効能

たまごには「身体を潤す」作用があるとされています。
たまご(鶏卵)は『陰液(血を含む身体の水分の総称)』を補う食材とされています。身体に潤いを与える働きがあるため、乾燥が気になる症状がある時に用いられます。
なかでも卵黄は『補血』の作用が強く、血が不足して起こる『血虚』や、それに伴う『陰虚』のケアに適しています。
例えば喉の渇き、皮膚の乾燥や髪のパサつき、不眠、寝汗、手足のほてりなどが気になる時に取り入れたい食材です。
一方、卵白は体にこもった熱を冷まし、肺を潤すとされています。中医学では喉の痛みや声枯れ、乾咳(カラ咳)などの症状に用いられます。
栄養学的の観点から見ると、たまごは「完全栄養食品」と呼ばれるほど優れた食材です。食物繊維とビタミンCを除くすべての栄養素を含んでいると言われており、特にタンパク質の質は非常に高く、体内で合成できない9種の必須アミノ酸を理想的な比率で含んでいます。
ビタミンやミネラルも豊富で、なかでも卵黄に多く含まれるビタミンAやEには、皮膚や粘膜を健康に保ち、乾燥を防ぐ働きがあります。
また卵黄に含まれる良質な脂質(レシチンや不飽和脂肪酸)は、細胞膜や皮膚の潤いを保つのに欠かせません。
これが『潤燥』=乾燥を和らげる効果につながります。
おすすめの薬膳書籍
薬膳の効能は、書籍によって記載内容が異なることがよくあります。これは薬膳が、数千年にわたる人々の実践と経験の積み重ねで発展してきた学問だからこそ。そんなとき頼りになるのが『先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版』。
複数の古典書をもとに、1184種類の食材が掲載されており、薬膳を実践するならぜひ手元に置いておきたい一冊です。

先人に学ぶ 食品群別・効能別 どちらからも引ける 性味表大事典 改訂増補版
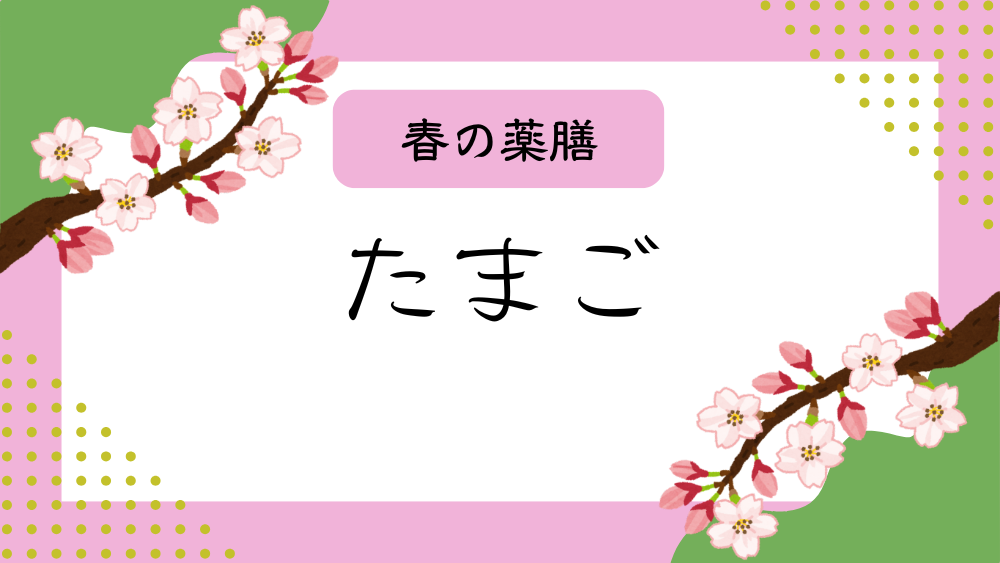


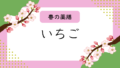
コメント